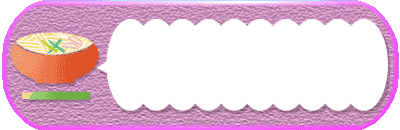
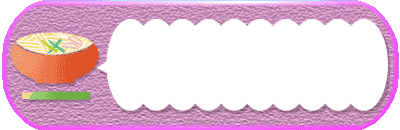
妾温泉
悠々亭味坊
南房総小滝町にある月岡温泉は、地元では「妾温泉」と呼ばれている。町名も温泉名も仮名だが、「妾温泉」と聞くだけで周辺住民のほとんどがそれと察するほど界隈では名が通っている。
この拙作が間違って公にされると、モデルのプライバシーを侵す恐れがあるし、なにより月岡温泉支配人金尾兼雄の逆鱗に触れ、同人に雇われている私は即日職を失うことになろう。
私はこの原稿を書くに当たって腹をくくった。
行き倒れになっても悔やむまい。その前に果たすべきことを果たせれば・・・
花冷えの四月某日、高山正子はいつものように、フロントと厨房と宴会場とをめまぐるしく往復していた。支配人金尾が経費を惜しみ、人手を極端に切詰めているからである。
「高さん、相変わらず忙しいな」客の一人が言った。「儲かってしょうがなかんべよ」
「おかげさまで。あたしの懐には入らないけんが」
「そんなこと言っていいんか。これに聞こえるっぺ」客は親指を立てた。
正子は慌てて後ろを振返った。体が太い割には神経が細いのである。
「びくびくするなよ、高さん。いないよ」客は笑って言った。
「こいつら、飲みすぎたで風呂はおいねえよ。ここで待たせてもらっていいかな」
別の客がロビーのソファーを指差した。
「ああ、いいよ。地べたで寝たら風邪ひくっぺ。桜が咲いてるちゅうに今夜はいやに冷えるもんね」正子は疲れていても愛想を忘れない。
「高さんが支配人だともっと繁盛するんだけんどな」
「あんで。そんなにうまくいくもんけ」正子は笑い飛ばした。
「おっと、これが来るぜ」客は声をひそめて小指を立て、脱衣場に向かった。
「おいねえな。なんか言われても気にしないでね」正子は客の背にささやいた。
二階の座敷から下りてきた銭先得子は、ソファーに座っている客を目敏く見つけた。
「ちょっと、高山さん。あの客、お金払ったの」
「酔っ払ったちゅうんで休ませてあげてんのよ」
「もらってないんでしょ?ロビーに入ったら入館料もらえってやかましく言われてるでしょうに」
得子は甲高い声を上げた。先輩の正子を立てるどころか、まるで下女扱いである。得子は客に対しても遠慮しない。ソファーの背にもたれている客に近づくと「お客さん、入館料いただきます」と切り口上に言った。酔客は得子の勢いにたまげたように財布を取り出した。「すいませんね、寝てるとこお越しちゃって・・・」
得子は客に尻を向けて「すいませんね」ともう一度言うとフロントに戻った。その態度からすまない気など毛頭ないのがわかる。
「高山さん、駄目じゃないの、ただで入らせちゃ」
得子は正子を叱った。客の前をはばかる気配はなく、むしろ客に怒鳴っているのである。
「ハーイ,気をつけまーす」
正子は言い捨ててフロントを離れた。
夜十一時近く、後片づけを終えて事務所に入ってきた正子は、いつものように私に愚痴をこぼした。
「文野さん、どう思う?あたしにはできないね、酔っ払いを外で待たせるなんて。ソファーがあるんだもの、座らせるくらいいいじゃない。ホント、人情ってものがないんだから、あん人は」
「支配人より始末悪いな。雇われてるくせに経営者面して・・・」
「元々は支配人が悪いのよ。お運びを妾にするなんてみっともないったらありゃしない」
「すごい神経だよな、妾と一緒にフロントに立つんだから恐れいりやのコンコンチキだ」
「文野さん、知ってるだろ?一円でも間違えると弁償。あたしはこっちのほうが我慢できんわ。風呂代、飲物代、料理代、足りない分はぜーんぶ弁償。多いときは黙ってポケットに入れちゃうくせにさ。金のことしか目に入らないんだから、二人とも。こういう人のことなんていったっけ?ケチとかしみったれくらいじゃ言い足りないし・・・」
「守銭奴。銭ゲバ。我利我利亡者。六日知らず。握ったら離さないって奴だ」
「とにかく並の神経じゃ一緒にやれるこんじゃない」
「高さんならどこでも勤まるよ。それに旦那も娘さんも働いてるんだし・・・いつだって辞められるだろ?」
「とんでもない。四十過ぎのバーさんなんてどこも雇ってくれないわよ。働かせてくれるだけでも上等と思ってるだけんが、あんまり悔しくてさ・・・」
正子は売上げを念入りに改めてから手提げ金庫を私の机の上に置いた。
「はい、お願いしますね。今日の売上げ、六十万越えてるよ。板さん一人、お運び二人、それに支配人と妾。五人でこれだけ稼ぐんだもの、容易なこんじゃないわ。目は回るし、膝は笑うし・・・」
高山正子は口とは裏腹に足取り軽く事務所を出ていった。
私は午前零時ごろまで、泊り客の世話、予約受付業務、館内警備などに忙殺され、温泉に隣接するログハウスの仮眠室に横になるのは午前一時を過ぎる。午前五時には起きて営業再開に備える。だからログハウスでの仮眠は、文字通りの仮眠で、熟睡とは縁遠い。
うとうとすると、枕もとの電話が突然鳴る。
頭が痛い。寒気がする。蕁麻疹が出た。油虫が這っている。毛虫が落ちてきた。カメムシが臭い。握り飯をつくれ。ビール持って来い。風呂に入っていいか。
次から次へと、注文、苦情、罵声のてんこ盛りである。
いやはやナイトフロントなどという和製英語に騙されて仕事に就いたものの、実情は奴婢下僕に近い。
正子の愚痴ではないが、「目が回る。膝が笑う」のはほんの序の口だ。血圧が上がる。心臓が踊る。足がむくむ。奥歯が軋る。ついには脳みそが泥沼状態・・・
仮眠時間前。私は今夜も定量二倍の精神安定剤を口中に放り込み、缶ビール三本を立て続けに胃袋に流し込んだ。
しばらくすると暗鬱な気分が晴れ、精神が高揚してくる。館内を走ろうか。温泉に飛び込むか。エイ、矢でも鉄砲でももってこい。
私は布団の上にどっかと胡坐をかき、歌舞伎役者のように両手を突き出し。周囲をハッタと睨めまわす。
月岡温泉は南総ゴルフ倶楽部敷地内にある。
ゴルフ会員権が投機の対象になった頃は、現金が毎日湯水のごとく会社の口座に振り込まれた。だから周辺の山を買い漁り、広大な敷地にゴルフ場はもとより、リゾートホテル、温泉、ボウリング場、テニスコート、屋外プール、大会議場兼レストラン、ログハウスとむやみに付属施設を建設しても、なお金の使い道に困るほどであった。
月岡温泉支配人金尾兼雄が右のような大盤振る舞いをしたわけではない。ケチなしみったれにできることではない。この投資をしたのは、金尾の実兄恩納好一である。金満一家に婿入りした好一は、不動産投機の時流に乗った。たちまちゴルフ場、ホテルを国内数ヵ所に建設し、ハワイのホテルを買収した。その上銀座に本社を構え、クラブ、ワインバーを経営するに至った。当時ダンプの運転手をしていた金尾兼雄は、好一に呼ばれて月岡温泉支配人に据えられた。いわば雇われ支配人である。
十数年後の今日、日本中が狂った不動産景気は泡と消えた。恩納好一が築いた企業グループに残ったのは、ゴルフ場にかかわる膨大な預託金返済額と過剰施設である。
南総ゴルフ倶楽部は皮肉なことに雇われ支配人を頂く月岡温泉が唯一収益を上げている。
むろん周辺住民の温泉好きに支えられて商売が成り立っているのだが、金尾兼雄は自分の手腕によると思っている。金尾の経営理念は「無駄を省く」である。従業員カット、賃金カット、経費カットで増収増益を図れると思い込んでいる。入館料・宿泊料金の値下げや、料理の品質向上、接客サービスの改善など、一言で言えば客を集める手立てには関心を示さない。すべて儲けが減る、あるいは金がかかるからである。
クラブハウスと温泉とを分かつ二股道の手前に桜が植えられて約二十年、今は大木となって満開の花を誇っている。
しかし私には花を楽しむ余裕はない。
私はボイラーを点検し、玄関前を掃いた。落ち葉がおびただしい。晩秋より多いかもしれない。私は毎朝毎晩この落葉に悩まされている。周囲の山々から際限なく降ってくるのを掃いていると、賽の河原にいるような虚しい気分に襲われる。老僧や大旦那が気紛れに掃くのとはわけが違う。仕事半ばで箒を投げ、
「行く春や・・・」
などと戯れ事に興じてはいられないのである。
午後七時過ぎ。私は息つく暇もなく厨房に入った。洗い物がたまっていれば手伝わなければならない。
お運びの一人、長島久子が膳を下げてきたついでに、フロントでトラブルが起きていると、板前の瀬川に告げた。
「成田から来てんのよ。キャンセルになりました、ハイ、そうですかで帰れると思ってんの」
茶色に髪を染めた女が正子に噛みついている。胸元をV字にカットしたブラウス、太腿をあらわにしたスカート、男から金を巻き上げようとの魂胆が露骨に見える身なりである。
「お断りしたはずだけんが・・・」
正子はうろたえていた。事情がのみこめないだけに、小心な正子は口ごもるばかりである。
支配人はトラブルと見るや、いち早く姿を消した。
「だから聞いてないって言ってるでしょ。予約の電話、あたしが受けてんのよ。ハチヤって客、ここへ連れてきてよ」
正子はあたふたと二階へ駆け上がり、肩で息をしながら戻ってきた。鼻の頭にうっすらと汗を浮かべている。
「すいませんね。お客さんの話じゃ、ウチにキャンセル頼んだらしいんだけんが、ウチは知らないんですよ」
「知らないじゃすまないでしょうが。あんたんとこのミスじゃないの。どうカタをつけんのよ。支配人呼びなさいよ」
茶髪女はなお言いつのった。
正子は支配人室に電話をかけ、事情を説明した。
支配人が受話器の向こうで怒鳴っているのだろう、正子のゆがんだ表情から、それがありありと伝わってくる。
「文野さん、電話代わって」
矛先がにわかに私に向かってきた。
「何で俺なのよ」
「お客さんが言うにはね、キャンセルの電話とったの男の声なんだって。とにかく早く支配人の話聞いて・・・」
正子はこの場を逃げたがっている。
私は濡れ衣を恐れた。しかしコソコソとネズミのように隠れるのはみっともない。ドブネズミ同然の姿をさらすのは元大統領一匹でたくさんだ、とテレビの画面を見たとき、私はそう思ったものだが・・・。
「はい、文野です・・・」
返事をするいとまもなく罵声がひびいた。
「キャンセルの電話受けたの、オマエだろ。何で連絡しないんだ。後始末はオマエがつけろ」
「いえ、私は知りませんが」
「とぼけるな。客は男の声だと言ってるんだ」
「洞口さんも男ですが」
「洞口はボーリング場だろ。事務所に出入りするのはオマエしかおらんだろうが」
「今日はボイラー室と玄関まわりの掃除で事務所には・・・」
「今日の話じゃない。きのう、おとといのこと言ってんだ。言い訳はもういい。とにかく始末をつけろ」
ガチャンと大きな音を立てて電話が切れた。
「支配人、来るの?来ないの?」
茶髪女がいきりたった。
支配人はトラブルの現場には現れない。一切を従業員に任せる。任せるというより責任をなすりつけ、自分はトラブルに直面しない。
「事情がありまして、のちほどご挨拶に伺うそうです」
「のちほどじゃ、間に合わないでしょ。一座敷、車代合わせて一万八千円。四人で七万二千円。払ってもらわなきゃ帰れないわよ」
「と言われましても、すぐにお支払いするわけにもいかないので・・・」
私は頭に血が上った。なぜ俺が矢面に立たなければいけないんだ。トラブルの元を作ったのは誰だ。始末をつけるのは支配人だろうが。さしあたりこの女どもを帰す手立てはあるか。私は困惑した。
「あたしが立て替えておくわ」
銭崎得子がいつのまにか背後に立っていた。「七万二千円。ちゃんと確かめてちょうだい」
銭崎の泥水を飲んできた量は、水商売の女に劣らない。茶髪女の見幕にたじろがず、レジから金を取り出すと、カウンターの上に並べた。あきらかに故意に並べている。
「領収書は文野さんがもらっておいて。これはあんたのツケよ」
得子は私に念押しした。
オイ、冗談じゃないぞ、何言ってるんだ。
私の睾丸は縮み上がった。得子は支配人に告げ口して、私の給料から差っ引くつもりなのだ。私が千円の金に四苦八苦しているのを得子は知っている。なのに七万二千円もの大金を押しつけようというのか。無関係なところで起きたトラブルの責任を私にとれというのか。
得子は私の抗弁を避けるというより、はなから聞き耳持たずといったそっけない態度で宴席に戻っていった。
私は目の前が真っ暗になった。立ち眩みだ。
私は普段から血圧が高い。上が百八十。下が百四十。今計れば上は二百を越えているだろう。
私は怒りに震えた。銭崎、金尾の顔が浮かんでは消える。そして洞口の顔が・・・
テニスコートとボーリング場の管理を任されている男。オレがオレがと何かにつけでしゃばりたがる年寄り。自称俳人にして詩吟クラブの幹事。これが今まで私の目に映っていた洞口の顔だった。
俳句業界には師匠を教祖のように崇める風習があるらしい。洞口は折りあるごとに虚子の名を出して写生が大切だなどと講釈をたれる。ある日、私は虚子の句を添削してやった。
去年今年肉棒ホトを貫けり
この方がわかりやすいとからかったら、原口は口をへの字に結んでその場を去った。
冗談を受けつけない「信濃の椋鳥」というべきか、下総「在の角蔵」というべきか。洒脱なところがまったくない「俳人」である。
「文野クン・・・」
洞口は年上であろうと古参であろうと平気でクンづけにする。そのくせ支配人と銭崎には卑屈なほど腰が低い。
「文野クン、何ぼんやりしてるんだ。掃いたらゴミ袋につめておけよ」
私は騒ぎに巻き込まれ、ロビーの隅で立ちすくんでいた。元凶は明らかに洞口だった。なのに洞口は騒ぎを外に、涼しい顔で私に指図している。
私はもとより下僕になったつもりでいる。便所掃除、皿洗い、草むしり、なんでもやるつもりだしやってきた。しかしドレイではない。命令されてやるわけではないのだ。ましてこの場合、洞口に指図され黙っていられるか。
私はやっと落葉をゴミ袋に詰め終わった。丸くなったゴミ袋を幾度となく蹴飛ばした。破れて腹から臓物が出るように落葉がこぼれるのを見て、私はようやく自分をなだめた。
バブル経済がはじける前、私はローンを組んで一戸建てを購入した。何年かたてば土地が値上がりし、ローンを全額返済しても、値上がり益で新築の戸建を買えると踏んだのである。くわえて当時はステップ償還という制度があった。五年間は返済の月額を二分の一に据え置き、六年目から返済額を倍に増やすという仕組みだった。企業の売上げや収益、土地、株、賃金、すべてが順調に上昇することを前提にした金融公庫の制度だった。行政がこの有様だったから、民間企業は末端の自営業までこの風潮に乗った。
私は自営業十三年で一千万円の頭金を貯めることができた。だから一千四百万のローンを組んでも不安はなかった。以降も右肩上がりの日本経済のおこぼれを頂戴できると思っていた。そこには一片の疑いもなかった。自分の才覚に対するウヌボレがさらに目を曇らせていた。
一九九二年頃を境に私の扱うアクセサリーが売れなくなった。不動産関連会社が数百億の負債を抱えて次々に倒産していた頃だ。間もなく私の商売も行き詰まった。すべてを整理し借金だけは残すまい、と私は自宅を売りに出した。一千四百万の値をつけてローン返済をもくろんだが買い手はつかなかった。バスも通わない片田舎の中古住宅に関心を持つ者はいなかった。バブル経済はとうにはじけていたのである。
私は電話を売り、電気、水道、ガスの供給を止め、自宅を出て、横浜の寿司屋に働き口を見つけた。
店から京浜急行と根岸線を乗り継いで約二十分、石川町の裏町に従業員用のアパートがあった。私は映画や小説で「たこ部屋」なるものを知っていた。しかし現実に目の当たりにし、しかも私がその住人になろうとは思いもよらなかった。
私は四畳半の和室をあてがわれた。同じ日に生麦店に採用された男と同居することになった。押入れがないので、二人分の布団と毛布が部屋の半ばを占めていた。掛布、敷布、
枕カバーは、辞めていった従業員の汗と垢と精液でシミだらけ。布団と毛布はねずみ色に変色していた。シャワーと便所は、四部屋に住み込んだ使用人八人が共同で使うらしい。さらに共同の台所が一つ。四畳半の板の間に流しと冷蔵庫が据えてある。私が入寮した翌日、関内店に雇われた男が入ってきた。この男は台所で寝ることになった。
私は入店早々へこたれた。なにしろ十七時間、ほとんどぶっ通しに働くのである。午前九時の開店準備から深夜二時、ときには夜明けまで、掃除、注文受け、料理運び、お膳下げ、皿洗い、飲物の入出庫と在庫調べ、レジ打ち、入出金の帳簿付けまで一人でやるのである。その間、親方に怒鳴られ、板前にからかわれ、客に文句をつけられる。自宅で商売するのに比べれば、誇張なしに生地獄だった。
仕事を終え、寮に戻り、シャワーを浴びると、欲も得もなく眠る。糞と味噌で煮しめたような夜具が煮干同然に干からびた体にふさわしかった。
入店三日目、夜明け方くたくたになって寮に戻ったとき、関内店の新入りが台所でビールを飲んでいた。座布団代わりにしている毛布を広げ「まあ、座っください。一杯やりましょうや」と誘ってくれた。
男は浅間と名のった。半年前までは電気工事会社の社長だったという。五十絡みのこの男はまだ精悍さを残していた。小柄だが肩幅があり、日に焼けた腕や胸には筋肉が盛りあがり、短く刈り込んだ髪は黒々としていた。
「不渡りをつかまされてね、ご覧のとおり丸裸さ」
浅間はパンツ一枚の裸姿で胡坐をかいている。
「家はどうしたんですか」
私は自分の一番気がかりな点を訊いた。
「女房と子供にくれてやりました。元女房ですがね。別れたんですよ。店も工場もみんな売って・・・家だけ残ったんで勝手にしてくれって置いてきたんです」
「気前いいというか、潔いというか、立派なもんですね」
「もともと裸一貫から始めたんだ、もう一度出直すよ」
浅間は脛をピシャピシャ叩いた。私は驚いて言葉が出ない。
「寿司屋の使い走りで終わりたくないからな。
職人の腕を盗んでやろうと思っているんですよ」
浅間は意気盛んだった。強い肉体がそれを支えている。
「私は夜逃げの準備をしてます。正直、これほどひどいところとは思わなかった」
「呑み屋とか食い物屋はどこも似たり寄ったりでね。住み込んだら二十四時間労働は当たり前よ。こぎれいなオフィスで事務とるのと違うから」
浅間は紛れもなく筋金入りの叩き上げだ。私のようなフリーター上がりのヘナチョコとは渡る世間が異なっている。
私はすでに戦いのカブトをぬいでいた。こぎれいなオフィスでなくてもいい。せめて十二時間労働で勘弁してくれる職場を探そう。
「浅間さん、お願いがあるんですけど。私は今日で辞めます。親方にそう伝えてもらえませんか。給料なんてどうでもいい。とにかく体がもちません。もともと血圧が高いんで、これ以上続けたらぶっ倒れそうだ」
「ああ、いいよ」浅間は軽く請合ってくれた。
「怪我と病気は自分持ちだ。ヨイヨイになってからじゃ遅いからな。オフクロさんが急病で入院したことにしておこう。給料も捨てることはない。もらえるようにしてやるよ」
実際に給料がもらえるかどうかは別にして、切羽詰った人間を励ませるのは、浅間が世間の広い苦労人だからだろう。私は近くの雑貨屋へ走り、なけなしの財布をはたいてビールを買った。浅間の厚意が嬉しかったし、なにより労働監獄からの脱走を祝いたかったのである。
私は脱走に成功した。浅間の計らいで一週間分の給料も振り込まれるはずだった。
私は身の回りの品を入れたナップザックを背負い、外房線H駅で下車した。改札口を出ると小さな木造の待合室がある。長椅子に座っていた老婆が乗客の捨てた「シケモク」を拾った。顔も手足も茶褐色に焼けている。日焼けというよりは南国の人間のように地肌にまで深く染みているようだった。蓬髪は肌とは逆に根元まで真っ白だった。「シケモク」を忙しなく吸った老婆は、乗客が散り、駅員が事務所の奥に引っ込むと、自販機の釣銭口に手を入れた。取り忘れの小銭を探しているらしい。
私の境遇はこの老婆と紙一重の隣にある。
私は焦燥にかられ待合室を出た。
タクシーを使えば十五分ほどで自宅に着く。
しかし目下の私は気軽にタクシーに乗れる身分ではない。私は初夏の陽射しを真向かいに浴びて歩き始めた。
舗装道路の両側には田んぼと畑が続く。稲が青々と育ち、ジャガイモの葉が揺れている。
田畑に人影はなかった。午後の強い陽射しを避けているのだろう・おおもとでは自然に任せながら時の主になれる生活。両側に広がる風景は、私にはただの田園風景ではなく、大地に根付いた揺るぎない生活に見える。
私は二時間余り歩き通して自宅に着いた。
Tシャツが胸と背中にべったりと張りついていた。
水が欲しい。しかし自宅は水ばかりか電気、ガスも止まったままだ。玄関脇に走行十万キロのポンコツが主人の帰りを待っていた。今では私に残された貴重な財産だ。かかってくれ。私は二度、三度、セルモーターを回した。五度目にエンジンがかかった。私は静かにアクセルを踏んだ。このポンコツをこれほど丁重に扱うのは初めてだった。
私はスーパーマーケットでポリタンクに水を入れた。米と卓上コンロを買った。これで三・四日は凌げるだろう。早く次の仕事を見つけなければ・・・明日から友人知人にあたり、ダメなら職安に行こう。
私は畳に大の字になったとたん、深々とした眠りに落ちた。目覚めたとき周囲は真っ暗だった。都会と違い、房総の片田舎は闇が濃い。私は手探りで仏壇のろうそくを灯した。
母の写真がぼんやりと浮かんでいる。母は入院どころか三年前に死んでいた。浅間はどんな顔をして親方を騙したのだろう。浅間の逞しさが妙に可笑しい。
母の写真の裏に父親の写真が隠れていた。
浅間の逞しさが一握りでも父にあったらと思う。父は結核にかかり、入院療養中に死んだ。私が中学二年のときだ。病気以前から保険にかかることを嫌がるケチでひ弱な男だった。父が入院するとすぐに母、私、三人の弟妹はその日暮しに追い込まれた。金が敵の生活が十年以上続いたのである。
米櫃に米が満ちるだけで幸せな気分になれるのは当時の後遺症だ。ところが還暦を過ぎた今、後遺症どころか当時の病気がぶり返した。私の米櫃は三分の一に満たない。私はろうそくの灯の下で、ジリジリと焦りの虫が鳴くのを聞いた。私は安定剤の力を借りてふたたび横になり、夜明けを待った。
私は平素の無沙汰にかまっていられなかった。頼れそうなところに電話をかけつづけた。
大学の後輩Fは労働大臣の私設秘書を勤めている。Fはこの種の依頼になれているせいか如才なく答えた。
「それはお困りでしょう。後援会の企業にあたってみますよ」
二年先輩のWは中学校の元校長だった。学生の頃と変わらない口調で気さくに応じてくれた。
「出入りの旅行業者に頼んでみよう。ホテルや旅館に働き口があるかもしれない」
期待の持てそうな返事は、FとWからの二件だけだった。しかしいずれにしろただちに決まる気配はなかった。
私は地元の職安に足繁く通う一方で、飯田橋、三田、川崎、千葉の職安に足を伸ばした。
どこも求職者で込み合っていた。担当の窓口に到達するまで半日かかるところさえあった。その混雑ぶりは大病院の待合室以上だった。言うまでもなく求職者の体力、気力は病気持ちの比ではない。相談に気合が入り、当然時間がかかる。係員は、役人風を吹かし、横柄な態度をとった昔の担当官と異なり、おおむね丁寧に応対していた。
私は他に負けまいとして、必死に担当者に窮状を訴えたが、いかんせん高齢者を求める企業は皆無だった。担当者はそれでも紹介状を書いてくれた。職安の建前として門前払いをくわせるのは、どうやらご法度になったらしい。
しかし紹介された会社・事務所の返事はつれないものだった。面接に応じてくれるところさえなかった。
一ヶ月が瞬く間に過ぎた。
私は細い糸を手繰った。まずWにおそるおそる結果を尋ねた。
「訊いたことは訊いたんだが・・・」
Wは言い渋った。その口調で、私は返事を容易に推察できた。
「どこも人を雇うどころか、人減らしに必死らしいな」
役所はどうなんだ。学校はどうなんだ。今年の年賀状に「年金で悠々自適」と書いてきたのは誰なんだ。私は激発しそうな自分をかろうじて抑えた。
Fは相変わらず如才なかった。
「連絡しようと思って、何度か電話かけたんですが、つながらなくって」
自宅の電話を売り払ったことは前に伝えたはずだ。Fは覚えていないのだろうか。
「それはとにかく、後援会に警備会社の幹部がいましてね、車の誘導員をお願いしたいという話なんですが」
「工事現場で旗を振る仕事か」
「ええ、ご不満でしょうが、しばらく我慢していただいて・・・将来はビルの管理にまわる機会があるそうですから」
私が脱走した寿司屋に同じ日に雇われた男がいた。この男は直前まで道路端で旗を振っていたのである。
「ここの方がましだっせ。旗振りはホンマきついよって。冬は手足の感覚のうなってな、しびれてもうて。夏は夏で体溶けてしまいそうや。それに運転する奴ら、わしらの言うこと聞かんし。なかにはツバキ、わしらの顔に吐きよる奴おるんや」
私が泣き言を漏らすたびに、男は旗振りのきつさをあれこれあげ、私をなだめた。男はいまだにローヤのような寿司屋にしがみついている。
「せっかく探してくれたのに断るのはなんだけど、他をあたってみるよ」
「そうですか。いや、私もやれと言われたら尻込みするでしょうね、あれはいかにもきつそうだ」
Fはあっさりと退き、電話を切った。
おい、待ってくれ。他に働き口はないのか。曲がりなりにも労働大臣の秘書だろうが。
私はしばらく受話器を置きかねた。細い糸ながらまったく切れてしまうと未練がつのる。
私は大海に投げ出されたような気分だった。取りつく島がない。だが観念して何もせず溺死を待つのはごめんだ。抜き手を切ってドーバー海峡を渡るような真似はできないが、わずかな時間にしろ、平泳ぎで波間を漂うことはできる。
私は地元の職安に絞って、毎日午前九時の開館を待った。東京はすでに外国と同じくらいに遠のいた。交通費が出せないのである。
私は職安の係員と顔見知りになった。とくに年配の担当者が熱心に斡旋してくれた。
「年齢制限に引っかかるけど、あたるだけあたってみてください。遠慮することはありませんよ」
年齢制限の壁は高く厚い。ベルリンの壁は崩れたが、年齢制限の壁はびくともしない。それは職安の求人カードが一目瞭然に示している。四十代後半に開いている門戸は極端に少ない。六十代は皆無に等しい。新聞の求人広告はさらに露骨に年齢制限を設けている。血眼になって仕事を探せば探すほど門前払いの冷たい現実が見えてくる。同じ土俵にあがって勝負できないのがいかにも辛い。腕に覚えのあるサムライなら、地団太踏んで口惜しがるだろう。世が世ならと腕を撫しつつ、笠張に日をすごす浪人の姿が目に浮かぶ。
例の年配の担当者が年齢制限を緩めて、紹介状を書いてくれるのは、自らの職探しの苦い体験に基づく厚意だろうか。あるいは職安での実績を踏まえて、個人商店や零細企業では、年齢制限は建前なのを承知しているのか。
いずれにしろ紹介してくれるだけでもありがたい。
私は壁にはじかれるたびに、自分の条件をはずし、ついにはゼロ以下に下げていた。
何でもいい。仕事がありさえすれば・・・
M市職業安定所は旧中央通りの外れにある。
中央通りは新旧ともにシャッターを鎖した店が多い。衣料、家具、寝具、玩具、書籍、金物、果物などそれぞれに店を構えていた名残が古びた看板からうかがえる。駅前の一等地からも大手デパートが撤退し、商店街全体が閑散としている。
唯一例外はM職業安定所の周辺で、今朝も九時前から人と車であふれていた。失業してもそこそこの車からおりてくる者はさほど深刻そうに見えない。なかには失業保険の手続きをとりに来る者もいるので、実態は見かけよりさらに深刻さの度合いが薄いのかもしれない。
だが私に限って言えば、事態は窮迫していた。米櫃の米は片手ですくって三食分。パン、麺類で補ってせいぜい一週間分の食糧しかない。財布には五千円札が一枚。食堂にしろ居酒屋にしろ、自由に飲み食いできた頃がまるで別世界の出来事だったように思える。どうしてこんな始末になったのだろう。私は混雑する職安の一隅で自分の順番を待ちながら、焦りの虫がジリジリ鳴くのを聞いた。
待つこと二時間余り、私の名前が呼ばれた。
例の年配の担当者が私を見ている。私は神妙に担当者の前に座り、求人カードの番号を示した。担当者は求人カードの原本を取り出し、紹介先に電話をかけた。ここまでは本人の事情にかかわりなく、日常の事務の流れでコトが進んでいった。
受話器を耳にあてている担当者の表情が明るくなった。心もち応答の声が弾んでいる。
「はい。ありがとうございます。さっそくうかがわせます」
担当者は電話をいったん保留にし、私に訊いた。
「今日の午後、空いてますか。面接してくださるそうですが」
空いているもいないもない。この時がくるのをまさしく一日千秋の思いで待っていたのだ。
「はい。空いています」
私は表情が崩れるのを抑えかねた。
「履歴書はありますか」
「はい。持ってきました」
担当者はふたたび電話をとりあげた。
「本日うかがうそうです。ご都合は何時が・
・ ・はい。承知しました。なにぶんよろしく
お願いします」
担当者は電話に軽く会釈した。笑顔がこぼれている。
「今日の五時、ゴルフ場の支配人室で面接してくださるそうです。しっかりアピールして決めてくださいよ」
担当者は自分のことのように喜んでいる。役人には珍しい人だ。むろん私も小躍りして職安を出た。
私は求人カードのコピーを改めて読み直した。
一九八六年南総ゴルフ倶楽部開業。一九八八年南総グランドホテル開業。二〇〇〇年月岡温泉開業。支配人金尾兼雄。従業員数八十人。基本給十八万円。交通費支給。賞与年二回。各種社会保険あり。昇給制度あり。退職金あり。定年制なし。職種夜間フロント。勤務時間午後六時から午前八時(仮眠時間四時間)休日月四回。
うん、悪くない。悪くないどころかこれ以上の仕事がこの先見つかるとは思えない。
私の胸は高鳴った。大学受験時の新鮮な緊張が蘇える。私は興奮を抑え、慎重に運転した。
自宅から約一時間。一市、二町、一村を通過して小滝町に入った。町に沿って走る国道を横切り、山道に入るとにわかに道幅が狭くなった。山道の両側から青葉若葉が伸びて、車の背中をこすりそうだ。南総ゴルフ倶楽部は清澄山系のなだらかな丘陵をいくつか崩して造成したらしい。
山道を登ること約五分。前方にマンション風の建物が現れた。求人カードにベージュ色、七階建てとあるから、あれがグランドホテルに違いない。道路左手に人口の滝が流れ、その脇に置かれた横長の巨石に「南総ゴルフ倶楽部」と刻まれている。
ホテル前から百メートルほど行くと倶楽部ハウスがあった。左右の植栽はゴルフ場らしく手入れが行き届いている。
私は玄関右脇の事務所の扉をノックした。
「どうぞ」
女の声が答えた。扉を開けると声の主が帰り支度をしている。ほかに事務員の姿はない。
「文野と申します。職安の紹介で参りました。支配人はいらっしゃいますか」
私は精一杯の猫なで声で訊いた。事務員は心得ていたように、私を支配人室に案内した。
正面の机の上に書類が雑然と積まれていた。支配人はその奥でスポーツ紙を広げていた。
支配人金尾兼雄は私の差し出した履歴書にざっと目を通すと性急に話し始めた。筋道だった話し方ではなかった。仕事についてあちらへ飛びこちらへ飛びしながら、肝心な給料その他の条件については触れない。私は支配人の要領を得ない説明に一つ一つ素直にうなずいた。ここでしくじってはならない。
「温泉とか、ホテルとか、持ち場が決まっているわけじゃない。要するに臨機応変にやってもらえればいいんだ」
支配人は唐突に切り上げた。
「明日から働けるかね」
横浜の寿司屋の親方同様即決だった。
「はい。今夜からでも」
私はすかさず答えた。
「細かいことは経理に訊いてくれ。ホテルの事務所にいるから。じゃ、よろしく」
支配人はあたふたと立ち上がった。忙しいのかイラチなのか、とにかく落ち着きのない男だった。しかし私にはそれが幸いした。腰を落ち着けじっくり選ぶ人事担当がいたら、私はこれまでどおり書類選考ではねられていたかもしれないのである。
私はコトがあまりに簡単に運んだので呆気にとられていた。支配人室を出て、ホテルの事務所に向かううちに、喜びより不安が大きくなった。もしかしたら横浜の寿司屋と同じ目にあうのかも・・・
怖いもの知らずの齢ははるか昔に終わった。以来、齢を食うたびに怯えが膨らんできた。世に言う負け組の典型的な症状だ。
経理の深井にあって話を聞くと私の不安は半ばあたっていた。
「給料は日給制で六千円。社会保険は難しいわね。職安にはぜんぶOKでお願いしているけど。定年制がないだけいいんじゃない?」
「雇用保険とか厚生年金とかはどうなるんですか?」
「厚生年金は会社が半分持たないといけないから、三年くらい前から新しく入った人はかけてくれないのよ。雇用保険のことは一応話してみるけど、期待しないほうがいいわ」
深井は定年制のある会社なら、退職しなければならない齢だろう。私より年上に見えるが、女だけに身綺麗にしているし、あたりが柔らかい。
「ボーナスは年二回支給とありましたが」
「それこそ雀の涙よ。小学生のお年玉の方が多いんじゃない」
深井は口を押さえて笑った。
まあ、いいか・・・わたしはすべてに目をつぶることにした。
なにしろようやく仕事にありつけたのである。さしあたり米櫃が空になってもびくびくしないですみそうだ。
「で、明日から何をやればいいんですか」
「当分はホテルでルームキーパーをやってもらうそうよ。お掃除したり、ベッドをつくったり、備品を管理したり。ルームは守川さんが主任。明日紹介するわ。ここは条件は悪いけど、従業員はみんな親切だから心配いらないわ」
こうして私は南総グランドホテルのルーム係として働き始めた。
六ヵ月後、夜間フロントが客とトラブルを起こした翌朝、深井に口頭で辞めると伝えたまま出社しないので、私が代わりを務めた。
その四ヵ月後、月岡温泉の雑用係が癌で入院し、私はその後釜に据えられた。実に将棋の歩より軽く扱われながら現在に至っている。
入社以来およそ一年が経過した。面接の日、深井が言ったとおり、南総グループの労働条件は悪い。並大抵の悪さではない。
去年の夏、お盆の繁忙期が一段落した後、深井が給料袋を配った。それぞれ一様に薄いので、私は給料明細が入っているのだろうと勝手に推測していたが、開いてみて心底仰天した。千円札が三枚。これが夏期ボーナスだった。
年末には音沙汰なし。今年正月にお年玉袋が配られた。中身は夏と同じく千円札三枚。いまどき三千円のお年玉では小学生でさえ怒るだろう。
かつてタイで起きたある事件が脳裏をよぎった。五バーツのコインをチップに与えられた娼婦が激怒し、日本人観光客を撃ち殺した事件だ。
本来ならタイの娼婦に倣うまでもなく、千円札三枚に激怒し、南総グループの経営陣をなぶり殺しにすべきものだろう。なぶり殺しが民主主義国日本では不穏当なら、せめて吊るし上げくらいはしてもよかろうものを、表立っては何もおきない。唯々諾々と従うだけだ。私も例外ではない。失職を恐れ、千円札三枚をありがたく頂戴した。
昨年支配人の面接を受けた直後、ホテルの事務所で深井が「従業員はみんな親切」と励ましてくれたのを、私は時々思い出しては苦笑する。
あれは新入りの使用人を安心させるための深井のリップサービスだった。お運びから妾に出世した銭崎を例にとれば一目瞭然だった。
役付から平へ、古参から新入りへ、要するに立場の強い者から弱い者へ、あからさまな脅しがあり、陰湿なイジメがあった。組織のあるところ、連綿と続く日本的風土が、月岡温泉に見られないはずがない。都会の風が入りにくい田舎だけに、むしろひときわ顕著だった。
と評論家風に解説している場合ではない。
さしあたりの被害者はほかならぬ私だった。
私は温泉に隣接するボウリング場の玄関に立った。背筋がぞくぞくし、足が震えるのは、花冷えのせいばかりではない。
私は静かにドアを開けた。客は一人もいなかった。閉館前だからでなく、人里離れたこのボウリング場はもともと客が少ないのである。
洞口は電源盤に向かっていた。場内の電気を切るのだろう。私には好都合だった。煌々と明かりがついていては邪魔が入りやすい。
私は太い柱にもたれてしばらく待った。電気が消え、場内の明かりは非常灯だけになった。洞口から私の影は見えないはずだ。
洞口が無警戒に近づいてきた。私はいきなり洞口の前に立った。洞口は腰を抜かさんばかりに驚いた。声にならない声をあげ、口をパクパクさせている。私はこれで勝てるとふんだ。案外肝っ玉の小さい奴だ。
私は学生の頃、柔道、空手を習った。試合ではいつも負けていたが、路上の喧嘩では遅れをとったことがない。素人相手なら、齢をとったとはいえ、多少の自信がある。
「挨拶は抜きだ。さっきのトラブルの原因はオマエだよな」
私は単刀直入に切り出した。
「・・・」
洞口は答を探している。
「えらい迷惑だぜ」
私はおっかぶせて言った。
「自分のミスを人に押しつけるのかね」
洞口はようやく返事を見つけた。
「それは俺が言いたいセリフだよ。キャンセルの電話を受けたの、オマエだろ?」
「知らんな」
洞口はいつもの図太いところを見せ始めた。余裕を与えてはならない。
「とぼけやがって・・・吐かせてやろうか」
私は身構えた。
「かかって来い。このボケ!」
洞口は顔をこわばらせた。あきらかに怯んでいる。
「黙ってないでナントか言えよ。オマエがやったんだろ」
私は問い詰めた。
洞口の目がうろたえて左右に助けを求めている。
私は勝機をつかんだ。顎に力いっぱいのパンチを浴びせた。
洞口はガクッと膝を折った。
私は勢い余ってたたらを踏んだ。腰高で拳を突き出したので、だらしなく体勢が崩れた。
私は前のめりの姿勢を立て直し振返った。
洞口はまだ片膝をついている。私は反動をつけ顎を蹴り上げた。洞口は仰向けに倒れた。
私は金的に蹴りを入れた。足の甲にナマコをつぶしたような感触が残った。洞口は下腹を抑えうずくまった。
「立てよ、腰抜け野郎!」
私は間合いをとりながら挑発した。
しかし洞口はむかってこなかった。ハナから戦意がなかったようにゆっくりと立ち上がり、戸締りをはじめた。鼻血を流しているが、大事には至らなかったようだ。私は内心ほっとした。私のパンチと蹴りは極端に威力が落ちているらしい。
「コンパニオン代、オマエが弁償しろよ」
私はノロノロと戸締りをする洞口の背中にとどめのセリフを浴びせ、ボウリング場を出た。
私はナニゴトもなかったように厨房に入り、山と積まれた汚れものを洗った。終始背後に注意を払っていたが、洞口は現れなかった。救急車もパトカーも登場しない。
どうなと勝手にしろ。
私は覚悟を決めた。
クビにしたかったらするがいい。だが、おとなしく切られはしない。ほかの使用人とは違うところを見せてやる。
救急車やパトカーは現れなかったが、支配人がいつものように慌しく厨房にやってきて、入口近くで怒鳴った。
「文野、オマエ、何やったんだ!」
私はゆっくり振り向いて怒鳴り返した。
「ヤキいれたんですよ。自分のミスを人のせいにしやがって。最低の野郎だ」
「洞口は警察を呼ぶと言ってるぞ」
「ああ、呼んだらいいでしょう!」
私は血が沸騰し支配人を殴るつもりになっていた。思いきり睨み返した。普段の倍返しだ。支配人は目をそらし、あたふたと厨房を去った。
私は洗い物を手荒く扱った。板前、お運びは息を潜めて私の様子を伺っている。
皿が激しい音を立てて割れた。
私は日常の仕事を終え、仮眠室にひきあげた。午前一時を回っていた。
私は仮眠室の玄関に向かって胡坐をかいた。傍らに厨房からひそかに持ち出した包丁を新聞紙にくるんでおいてある。
依然として警察や消防の現れる気配はない。
支配人からも洞口からも何も言ってこない。
私は口中に安定剤を放り込みビールをあおった。しかし興奮はおさまらず、かえって両膝の貧乏ゆすりが激しくなった。私は残りの錠剤すべてをビールと一緒に胃袋に流し込んだ。
しばらくすると周囲に垂れ込めていた灰色の霧が晴れた。トクトクトク・・・血液の流れが聞こえる。
私は立ち上がり、玄関脇にはめられた大鏡を見た。そこに洞口の姿が映った。
私はボウリング場の場面を反芻した。
左ストレート一発。洞口が膝を折る。うつむいた顔面に右足の蹴り。仰向けになる洞口。左足の蹴りが金的に命中。
私は姿見を相手に、パンチを浴びせ、蹴りをいれた。
姿見に別人が現れた。半白の頭。たるんだ頸。シミだらけの赤ら顔。突き出た下腹。醜い年寄り・・・ああ、このオレだ。
私は幻影を払うように、夢中で拳を振るい、足蹴りをいれた。必死になればなるほど打撃は鈍く弱い。息が切れ、足元がふらつく。しだいに例の灰色の霧が周囲に迫ってきた。
私は目を瞑り息を整えた。ふたたび目をあけると姿見の中に支配人がいる。私はそっと包丁を取り上げた。包丁を握った右手を腰に寄せ、左手を突き出して間合いをはかる。
一閃!
支配人の片耳を削ぐ。
一閃!
片目を抉る。
支配人が両手を合わせ命乞いをしている。
今頃謝っても手遅れだ。全従業員の汗と涙と怒りと恨みを晴らしてやる。
私は思い切り顎を蹴った。敵は仰向けに倒れた。馬乗りになり、両手で包丁を握り、振り下ろした。
一突き、二突き・・・血飛沫が上がる。
私は流れる汗を掌でぬぐった。現実か幻覚か、私にはもう見分けがつかない。
刃渡り二十センチの出刃が半ば以上埋もれている。それは垂直に支配人の心臓を貫いているように見える・・・